2024年04月25日
障がい者雇用の法定雇用率とは|達成できない場合はどうなる?

目次
企業の障がい者雇用の担当者のうちほとんどの方が、「法定雇用率」という言葉を聞いたことがあるでしょう。法定雇用率とは、民間企業などが従業員数のうち何パーセントの割合で障がいのある方を雇用するかを定めたものです。
ただ、法定雇用率を調べてみると、数字がいくつも出てきて「結局自社は何人雇う必要があるのか」と疑問がある方もいると思います。以下の条件を満たすことが必要です。
この記事では法定雇用率制度の概要や、具体的な率の数字、達成できない場合の対応などを解説していきます。
法定雇用率とは
 法定雇用率は、国の障害者雇用率制度によって定められた、民間企業などが何人障がいのある方を雇う必要があるかを決める数値のことです。
法定雇用率は、国の障害者雇用率制度によって定められた、民間企業などが何人障がいのある方を雇う必要があるかを決める数値のことです。
法定雇用率は令和5年時点で民間企業は2.3%と定められており、43.5人以上の従業員がいる企業が1人以上の障がいのある方を雇う義務が生じるとされています。
また、法定雇用率は段階的に引き上げられていくことが予定されており、令和8年7月からは2.7%、つまり37.5人以上の従業員がいる企業で障がいのある方の雇用義務が生じることになります。障がい者雇用を検討している企業の担当者の方は、将来のことも見据えて準備をしておくようにしましょう。
なお、障害者雇用率は計算式があり、民間企業では(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数) ÷(常用労働者数+失業者数)によって導き出されています。
令和8年度にかけて障害者雇用率は2.7%へ段階的に引き上げ
先程の計算式をもとに、令和5年度には法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決まりました。
しかし、企業が雇用計画を立てられるように段階的に2.7%まで引き上げられていく予定です。詳しくは表にまとめましたので、参考にしてください。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和8年度 | |
| 法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7 |
| 障害者雇用の対象となる事業主 | 従業員43.5人以上 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |
なお、国や地方公共団体は法定雇用率が別に設定されており、令和8年から3.0%になる予定で、民間企業と同様に段階的に引き上げられていくことになっています。
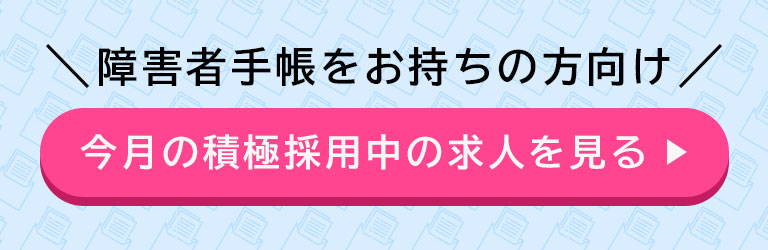
障がい者雇用の対象者
 障がい者雇用は基本的に障害者手帳を所持している方が対象となります。
障がい者雇用は基本的に障害者手帳を所持している方が対象となります。
【障がい者雇用の対象者】
- 身体障害者手帳を所持している身体障害のある方
- 療育手帳を所持している知的障害のある方
- 精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害、発達障害のある方
なお、以前は知的障害のある方と身体障害のある方のみでしたが、平成30年度からは精神障害のある方も雇用が義務付けられました。
従業員の算定方法
また、障害者雇用率制度では、雇用した障がいのある方の週の所定労働時間や障がいの程度に応じた従業員数への算定方法が定められています。
こちらも表にまとめましたので、ご確認ください。
| 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 (令和6年度予定) |
|
| 身体障害のある方 | 1 | 0.5 | – |
| (重度の場合) | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害のある方 | 1 | 0.5 | – |
| (重度の場合) | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害のある方 | 1 | 0.5※ | 0.5 |
※以下の2つの条件を満たす方は1とみなされます。
- 新規雇用から3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合
- 令和5年3月31日までに雇用され、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
現在は20時間以上の方が対象となっており、令和6年度から10~20時間未満の方も算定対象となります。
ここまで見てきたように、障がい者雇用率制度は年々変化がありますので、担当者の方は定期的にチェックしておくようにしましょう。
法定雇用率を達成できない場合はどうなる?
 法定雇用率によって障がいのある方を雇用する義務のある企業などが、定められた人数を雇うことができないときには、納付金の徴収や行政指導などが行われます。
法定雇用率によって障がいのある方を雇用する義務のある企業などが、定められた人数を雇うことができないときには、納付金の徴収や行政指導などが行われます。
【法定雇用率を達成できない場合】
- 障害者雇用納付金の納付義務が発生する(従業員数が100名を超える企業)
- 行政指導が入る
達成できない場合は納付金を収める必要がある他、ハローワークから行政指導が入る可能性があります。それぞれ具体的に紹介します。
障害者雇用納付金の納付義務が発生する
従業員数が100名を超える企業が法定雇用率を達成できない場合は、障害者雇用納付金を収める必要が生じます。
障害者雇用納付金とは、障がいのある方を雇用する際の経済的負担などを公平にするため、法定雇用率未達成企業から納付金を徴収し、多く雇用している企業へ助成する制度です。あくまで、障がい者雇用を促進することが目的であり、罰金ではありません。
納付金は不足している人数一人につき月5万円で、法定雇用率を満たすまで払い続ける必要があります。
行政指導が入る
法定雇用率を達成できない場合はハローワークから、雇用率達成指導という名称の行政指導が行われます。
具体的には、まずハローワークから雇入れ計画作成の命令があり、その計画の状況が思わしくない場合にはさらに指導が入ります。それでも達成できない場合には、特別指導や企業名の公表が行われる場合もあります。
行政指導が入ると、計画作成のための稼働やハローワークへの報告などにより、業務の負担が増えてしまうことも考えられます。
障がい者雇用の手順
 ここでは、実際に障がい者雇用を実施する際の手順をお伝えします。障がい者雇用をこれから始めようと考えている担当者の方は参考にしてみてください。
ここでは、実際に障がい者雇用を実施する際の手順をお伝えします。障がい者雇用をこれから始めようと考えている担当者の方は参考にしてみてください。
【障がい者雇用の手順】
- 障がい者雇用の理解を深める
- 配属部署などを決める
- 環境設備を整える
- 採用活動を行う
- 職場定着の取り組みを行う
このように、まずは障がいについての理解を深めることが大事です。そのうえで、配属部署や職場環境の整理を行うなどの準備を進めていくと、スムーズに障がい者雇用に取り組めるといわれています。
ただ、「具体的にどう進めたらいいのかわからない」という声もよく聞かれます。そういったときは、ハローワークなどの公共機関や、障がいのある方向けの人材紹介サービスなどに相談することでアドバイスや研修などを受けることができます。
障がい者雇用を円滑に進めていくためにも、このような障がいのある方と企業双方と接してきた専門家を頼ることも一つの方法です。
まとめ
法定雇用率とは、企業などがどれくらいに障がいのある方を雇用する義務があるのか定めた割合のことです。
現在の法定雇用率は2.5%ですが、令和8年度からは2.7%に引き上げられる予定で、従業員37.5人以上の企業で障がいのある方を一人雇用する計算になります。
また、法定雇用率が達成できない場合は従業員数に応じて、納付金の徴収やハローワークからの行政指導が入る可能性もあります。
障がい者雇用に関わる制度は年々変化しています。企業の担当者の方は先を見据えて計画的に進めていくことが大事です。「何から始めたらいいのかわからない」「どう計画立てたらいいのか悩んでいる」という場合は、ハローワークや民間の人材紹介サービスなど障がい者雇用に詳しい専門家の意見も取り入れていくと進めやすくなるでしょう。
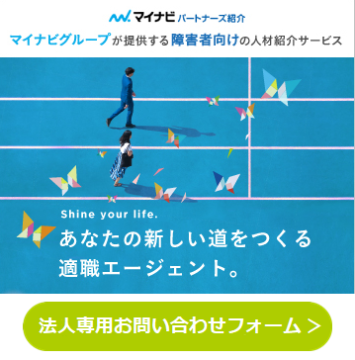
| 【本記事監修者】 佐々木規夫様 産業医科大学医学部医学科卒業。 |