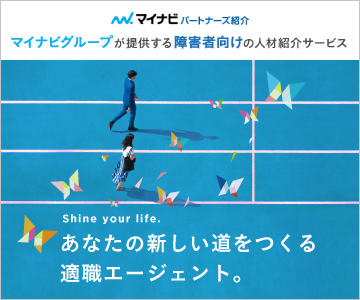2024年03月31日
精神疾患や精神障害の方におすすめの仕事とは?|長く働き続けるためのポイントを紹介!

目次
精神疾患のある方が就職を探す場合、どのような仕事が自分に向いているか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
就職してからも、仕事中に困りごとが出て迷惑をかけてしまうのではと、心配することもあるかもしれません。
本記事では、仕事中の困りごとにどのような対策が有効か、同じ職場で長く働くにはどのような点に気をつければよいかを説明しています。
就職に悩まれている精神疾患のある方は、ぜひ最後までご一読いただき参考にしてみてください。
精神疾患とは

精神疾患とは、気分の落ち込み・幻覚・不眠・妄想など、心と体にさまざまな症状がでるために日常生活に支障がでてくる病気です。
一般的によく知られている精神疾患としては、次の種類が挙げられます。
- 大うつ病性障害(うつ病)
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 発達障害
- 解離性障害 など
よく似た言葉に「精神障害」があります。精神障害は、精神疾患が原因で日常生活が困難となっている状態のことを指します。
精神疾患の種類
精神疾患には、さまざまな種類があります。主な精神疾患の特徴を、次の表にまとめました。
【主な精神疾患の種類】
| 精神疾患の種類 | 特徴 | 障害者手帳の対象 |
| 大うつ病性障害 | 「一日中気分が落ち込む」「何をしても楽しめない」といった精神症状と「眠れない」「食欲がない」「疲れやすい」などの身体症状が現れる | ○(精神障害者保健福祉手帳) |
| 双極性障害 | 気分が盛り上がり活動的な躁状態と、気分が落ち込み無気力となるうつ状態を繰り返す | |
| 統合失調症 | 脳のさまざまな働きをまとめることが難しくなり、幻覚や妄想などの陽性症状や意欲低下などの陰性症状が現れる | |
| 発達障害 | 生まれつき見られる脳の働き方の違いにより、行動面や情緒面に特徴のある状態(こだわりが強い、落ち着きがないなど) | |
| 解離性障害 | 意識や記憶に関する感覚をまとめる能力が一時的に失われ、健忘や離人感などの症状が現われる |
精神障害者福祉手帳は、すべての精神障害が対象となりますが、必ず手帳が交付されるわけではありませんので、詳しくは主治医や市町村の障害者福祉の相談窓口に相談するとよいでしょう。
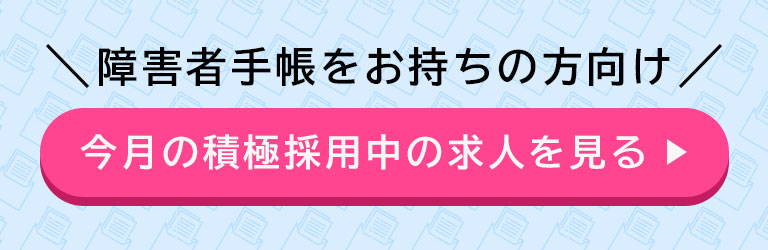
精神疾患のある方が仕事をするうえで困ることと対策

精神疾患のある方が仕事をするにあたり、次のような困りごとが考えられます。
【精神疾患のある方が仕事中に困っていること】
- 人よりも疲れやすいことがある
- 体調が安定しにくいケースがある
- 職場や周りの理解が得られにくいことがある
困りごとは個人によって千差万別であり、同じ病気でも症状の違うことはよく見られます。「どのようなことで困るのか」「ストレスを感じるのはどのような状況か」など、自分自身の状態をよく知っておくことも大切です。
人よりも疲れやすいことがある
精神疾患のある方の中に、疲れを感じやすいことで悩まれる方がいらっしゃいます。
精神疾患があることで、精神疾患のない方と同じ仕事量をこなしても、疲れ度合いの異なる場合があります。そのことを相談できず気にしすぎてしまい、ストレスでさらに疲れてしまうことがあるかもしれません。
また、幻覚・妄想・気分の落ち込みなど、病気が原因で日常生活を送るだけでも労力を使う場面が考えられます。
できれば職場に相談してみて、業務の負担を減らしてもらう、適宜休憩するなどの対策を講じてみるとよいでしょう。
体調が安定しにくいケースがある
環境の変化やストレスなどが原因で体調が悪化し、精神疾患の症状が悪化するケースに悩まれる方もいらっしゃいます。
日によって体調が変わり仕事のパフォーマンスに影響することや、急に気分が落ち込み動けなくなる可能性も考えられます。とはいえ、仕事をしている最中は周囲に気を遣い、体調のことをなかなか言いだせないものです。
服薬している方は日頃から薬の飲み忘れに注意し、体調が悪くなりそうな前兆を感じたら早めに休憩したり、相談したりするなどして、できる範囲で工夫してみましょう。
職場や周りの理解が得られにくいことがある
精神疾患は見た目ではわかりにくいため、周囲から理解を得るのに難しい場面があります。
病気によって体調が悪い場合でも、周囲から見ればサボっていると思われることがあるかもしれません。また、症状のために人とコミュニケーションを取るのが億劫であったり、スケジュール管理がうまくできなかったりと、周囲の方に誤解を与えてしまうことも考えられます。
体調が優れない時は、予め周囲に症状を伝えておくことで、理解や協力を得られることも多いです。障がいを職場に開示するのが難しい場合は、家族や信頼できる方に相談してアドバイスをもらうのもよい方法です。
精神疾患のある方が長く働き続けるためのポイント

精神疾患のある方が長く仕事を続けるためには、次のポイントを知っておくとうまくいく可能性が高まります。
【精神疾患のある方が長く働き続けるためのポイント】
- 精神疾患がある方が多く働く仕事を知る
- 柔軟な働き方ができるか確認する
- 困った時に相談できる窓口が設置されているか確認する
- 自身の障がいや得意不得意を明確にする
- 障がい者雇用枠での就職も選択肢の一つ
- 精神疾患がある方向けの就労支援を活用する
ただし、これらの項目がすべての方に当てはまるわけではありません。情報として知っておき、必要と思われることがあれば活用するとよいでしょう。
精神疾患のある方が多く働く仕事を知る
精神疾患の有無によって、職種が限定されることはありません。
ただし、精神疾患の特性や症状によって向いている仕事は異なります。また、同じ病名でも症状には個人によって差があるため、一概にどのような仕事がおすすめかと断言するのは困難です。
令和3年度における、ハローワークを通じて就職した状況を一覧にしましたので、就職先を選ぶ際の参考にしてみてください。
【令和3年度・精神障がい者の就職状況(上位のみ)】
| 順位 | 職種 | 割合(%) |
| 1 | 医療福祉 | 41.5 |
| 2 | 製造業 | 11.4 |
| 3 | 卸売・小売 | 10.5 |
| 4 | サービス業 | 9.9 |
| 5 | 運輸郵便 | 3.6 |
参照元:厚生労働省「令和3年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」
柔軟な働き方ができるか確認する
柔軟な働き方のできる職場であれば、長く働き続けられる傾向にあります。
精神疾患は、長期にわたった治療が必要となることがあります。自分のペースを守れる職場であれば、生活のリズムが安定して早く寛解に近づけられるでしょう。
【柔軟な働き方の一例】
- フレックスタイムが導入されている
- 時短勤務・在宅勤務を選択できる
- 通院による休暇を認めてもらえる
- 症状によって出勤場所や業務内容を考慮してもらえる
- 体調によって適宜休憩が認められている など
上に挙げた配慮を認めてもらえる職場であれば、臨機応変に対応できるため働きやすさを感じられます。
困った時に相談できる窓口が設置されているか確認する
困ったときに相談できる窓口が設置されている企業であれば、働く上で安心感を得られるでしょう。
最近、従業員のメンタルヘルス対策に取り組む企業が増えてきました。具体的な取り組みについては、次の事例が挙げられます。
| 【企業によるメンタルケアへの取り組み事例】 ● 経営者主導による、メンタルヘルス対策の推進 ● 事業場内の産業保健スタッフや事業場外の専門家による、メンタルヘルスケアの提供 ● 社内の相談窓口の利用促進・コミュニケーション体制の推進 ● 衛生委員会でのメンタルヘルス対策・過重労働低減の取り組み など |
労働者が50名以上いる職場(事業場)では産業医の選任が義務づけられているため、健康上の不安面を相談することも可能です。
職場内に気兼ねなく相談できる窓口や人材がいれば、精神的にも楽に仕事ができるでしょう。
自身の障がいや得意・不得意を明確にする
就職にあたっては、自分にある障がいをよく理解し、できることとできないことを明確にして知っておくことが大切です。
精神疾患のある方でも、自分にある症状を十分に理解できていない方もいらっしゃるのは事実です。「どんなときにストレスを感じるか」「どんな作業に困るのか」「どういう状況になると症状が出るのか」など、自己分析をしっかり実施することで、就職時のミスマッチを防ぎやすくなります。
自己分析するとマイナス面に焦点を当てがちですが、自分の得意なことをしっかり洗い出してアピールするのも大切です。自分の障がいを理解して面接時に具体的に伝えておけば、自分の特性に合った職場へ就職できる可能性が高くなるでしょう。
障がい者雇用枠での就職も選択肢の一つ
障害者手帳を持っていれば、障がい者雇用枠の利用が可能です。精神疾患のある方には、次の3種類の雇用枠が利用できます。
| 雇用枠の種類 | 概要 |
| 障がい者雇用枠 | ● 障害者手帳(精神疾患の場合「精神障害者保健福祉手帳」)を保有している人を対象とした雇用枠 ● 合理的配慮(障がいの特性上必要だと認められる場合、就業時間の短縮や就業時間内の通院、休憩などの配慮)を求められる ● 障がい者雇用の担当者が企業に在籍し、仕事をするうえで困ったことなどを定期的に相談できる ● 職種を限定される可能性がある |
| 一般雇用枠(障がいオープン) | ● 一般の雇用枠で、障がいのあることを開示して就職する ● 合理的配慮を求められる ● 職種を限定される可能性がある |
| 一般雇用枠(障がいクローズド) | ● 一般の雇用枠で、障がいのあることを開示しないで就職する ● 合理的配慮は受けられない ● 職種の限定はない |
精神疾患のあることを開示して就職した場合、合理的配慮を求められるのが大きなポイントです。合理的配慮を求める権利は、法律によって保障されています。
なお、一般雇用枠においては配慮の範囲・考え方・対応できる設備が企業によって異なるため、必ずしも望む配慮が得られるわけではないことに注意が必要です。また、精神疾患を開示せずに一般雇用で働く場合、どの職種にでも応募可能ですが、合理的配慮は基本的に受けられません。
精神疾患を開示する義務はないため、職場に伝えるかどうかは個人の自由です。どの雇用枠が合うかは個人によって異なるため、よく検討して応募するようにしましょう。
精神疾患のある方向けの就労サービスを活用する
精神疾患のある方が仕事を探すにあたり、悩みや不安を相談できる就労サービスが数多くあります。具体的には、次の就労サービスが利用可能です。
【精神疾患のある方が活用できる就労サービス】
- 就職移行支援事業所:一般就労を目指す障がいのある方に対して、就労に必要な知識と能力の訓練をする通所型のサービス
- 地域障害者職業センター:障がいのある方に対して、職業リハビリテーションサービスを提供するサービス
- 障害者就業・生活支援センター:住居の近隣地域において、社会生活に対して一体的な支援をおこなう機関
- ハローワーク:全国に設置している公共職業安定所で、仕事に関する情報提供や就職相談など実施している
- 転職エージェント:求職者個人にキャリアアドバイザーがつき、就職相談から就職後のフォローまで、一貫してきめ細やかなサポートを受けられるサービス
転職エージェントや各種就労サービスでも、転職後も仕事の相談ができるといったアフターフォローを受け付けてくれるところがあります。もし就職後に困りごとや相談ごとが出てきた場合、遠慮せずに活用しましょう。
まとめ
精神疾患の症状は人それぞれ違うため、職場へ理解を得て働くことが大切です。長く働くためには自身の症状を知り、周囲へ説明できるようにするとよいでしょう。
また、働きやすい職場や職種を選ぶことも重要です。障がい者雇用枠の利用や就労サービスを積極的に活用して、自分の特性にあった働き方を見つけていきましょう。転職後にフォローのある転職エージェントや各種就労サービスを利用することで、就労後の安心感も得られます。ぜひ利用を検討してみてください。
| 【本記事監修者】 佐々木規夫様 産業医科大学医学部医学科卒業。 |