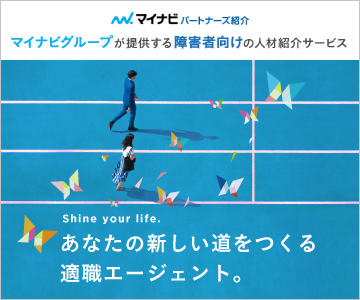2024年03月31日
学習障害(LD)の方の仕事選びのポイント|働きやすくするための工夫も紹介!

目次
学習障害(LD)の方が就職を探す場合、さまざまな困りごとや悩みに直面することもあるでしょう。
本記事では、学習障害の方が仕事をする上での困りごとと対策、長く働ける職場選びのポイントについて解説しています。
利用できる就労支援サービスの紹介もしていますので、利用を検討されている方はご一読いただき、参考にしてください。
学習障害とは

学習障害(LD:Learning Disability)は発達障害の一つで、知的発達には遅れがないものの、学習に必要な基礎的能力のうち特定分野にのみ困難が生じる状態をいいます。おもな症状の例としては、次が挙げられます。
| 読字障害(ディスクレシア | 文字を読みにくい傾向にある |
| 書字表出障害(ディスグラフィア) | 文字や文章を書くのが難しい傾向にある |
| 算数障害(ディスカリキュリア) | 数字の理解や計算が難しい傾向にある |
学習障害には、文部科学省と医学的な定義の2種類あります。文部科学省の定義では「聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力」と幅広い領域が含まれる一方、医学的な定義では「読字の障がいを伴うもの」「書字表出の障がいを伴うもの」「算数の障がいを伴うもの」の3種類に内容が限定されるのが大きな違いです。
また、医学的な定義では「限局性学習症(SLD:Specific Learning Disorder)」と呼ばれます。
発症の原因については、中枢神経の機能障害と考えられていますが、現在のところ医学的には明らかにされていません。大人になってから発症する例はないことから、先天性のものではないかと考えられています。
障害者手帳の種類と等級
障害者手帳は、何らかの障がいのある方が申請して交付される手帳です。障害者手帳には次の3種類があり、学習障害は発達障害にあたるため「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象となります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
精神障害者福祉手帳には1級から3級まで等級があり、障がいの程度によって等級が決められます。
■精神障害者保健福祉手帳の等級
| 等級 | 判断基準 |
| 1級 | 周囲の援助がなければ、日常生活に著しい制限をうけている状態 |
| 2級 | 1級よりは症状は軽いが、日常生活にかなり制限を受けている状態 |
| 3級 | 2級よりは症状は軽いが、日常生活や社会生活に制限がある状態 |
学習障害の場合、お住まいの市町村の担当窓口で申請手続きをおこないます。申請後は各自治体の精神保健福祉センターで審査され、認められると手帳が交付されます。
なお、学習障害の方は申請対象となっているのですが、必ず手帳が交付されるわけではありません。詳しくは、主治医や障害者福祉窓口で相談してみるとよいでしょう。
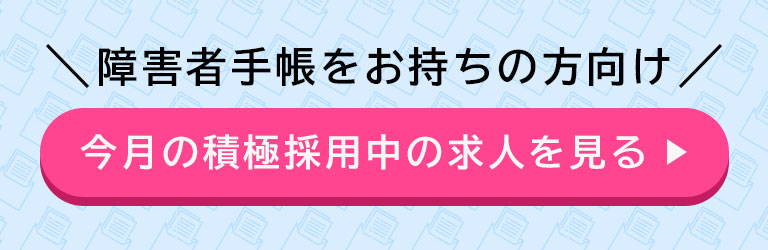
学習障害の方が仕事をするうえで困ることと対策

学習障害の方が就職をするにあたっては、次のような困りごとが考えられます。
【学習障害の方が仕事をするうえで困っていること】
- 資料やマニュアルの文章を読みづらいケースがある
- メモを取ることが難しい場合がある
- 時計が読めずスケジュール管理が難しいことがある
- 計算に時間がかかることがある
これらの困りごとは、学習障害の種類や個人の状態によって内容が異なります。「どのようなことに困っているのか」「どのようなことにストレスを感じるのか」「どうすれば困りごとを回避できるのか」など、自分自身の状態をよく知っておくことが大切です。
資料やマニュアルの文章を読みづらいケースがある
読字障害の場合、資料やマニュアルに書かれた文章をうまく読み進められないケースが考えられます。
【有効な対策・工夫】
- 読んだ部分に印やマーカーを入れる
- 読み間違いしにくいユニバーサルデザインフォントへ変更する
- 職場の方に読み上げてもらい、口頭で説明を受ける
- パソコンやスマートフォンの文章読み上げアプリを使う など
長い文章の読み取りは難しいけれど短文なら理解できる場合、読んだ部分に印を入れる、マーカーを引く、読み間違えしにくいフォントへ変更するなども有効な対策です。短文でも難しいと感じられる場合は、職場の方に読み上げてもらうか、読み上げソフトを利用してみるとよいでしょう。
メモを取ることが難しい場合がある
読字障害の場合、黒板やホワイトボードに書かれた文章が読みにくく、メモやノートへ書き写すのに困るケースが考えられます。また、書字表出障害の場合には、説明されたことをメモするのに困る可能性があります。
【有効な対策・工夫】
- ボイスレコーダーやアプリを使って録音する
- カメラで録画・写真撮影する など
メモを取るのが難しい場合、ボイスレコーダーやスマートフォンで録音するとよいでしょう。黒板やホワイトボードを写真に撮るのもよい方法です。動画を撮って映像として残せれば、目と耳から情報が得られるのでおすすめです。
ただし、録画・録音・写真撮影は、情報漏えいの観点で問題視されることもあります。録画・録音・写真撮影をしたい場合は、責任者に事情を説明して許可を取るようにしましょう。
時計が読めずスケジュール管理が難しいことがある
障がいによって時計を読むのが困難な場合、時間管理の難しい場面の出てくる可能性があります。
【有効な対策・工夫】
- アラームやリマインダー機能を使う
- 上司・同僚に声かけをお願いする
- チームでの業務に配置転換をお願いする など
スケジュール管理が難しい場合、スマートフォンのアラーム機能やリマインダー機能を活用するとよいでしょう。決まった時間にアラームが鳴ることで、時間管理がスムーズになります。
スマートフォンを持ち歩けない職場であれば、上司や同僚にお願いして、時間になれば声をかけてもらうようにするのもよい方法です。また、個人作業ではなくチーム作業に配置転換してもらえれば、周囲とタイミングを合わせて行動できます。
計算に時間がかかることがある
障がいによって数字の理解が難しく、自分で計算をするのに困るケースもあります。
【有効な対策・工夫】
- 計算機や計算アプリを使用する
- 表計算ソフトで計算式を組んでおく
- 計算が不要な職場へ配置転換を申し出る など
計算に時間のかかる際は、計算機やスマートフォンの電卓機能の活用がおすすめです。音声入力に対応しているものや、計算の履歴をさかのぼれる機能があるものなど、自分の利用しやすいものを選ぶとよいでしょう。
パソコンで毎回同じ計算が必要な際は、表計算ソフトで計算式をあらかじめ組んでおくのもよい方法です。自分で式を組めないときは、作成できる方に作ってもらうようお願いするとよいでしょう。それでも困難だと感じる場合、会社に障がいのことを相談して、計算の不要な職場へ配置転換してもらうのも一案です。
学習障害の方が長く働ける仕事・職場選びのポイント

学習障害の方が長く働ける仕事・職場選びの方法として、考えられるポイントは次のとおりです。
【学習障害の方が働きやすい仕事・職場選びのポイント】
- 障がい者雇用枠を検討する
- 自分のできること・苦手なことを明確にする
- 困った時に相談できる窓口が設置されている
それぞれについて次に説明します。
障がい者雇用枠を検討する
障害者手帳を交付されている方は、障がい者雇用枠を検討するのも一つの方法です。学習障害の方は、次の3つの雇用枠を選択できます。
【雇用枠の選択肢】
|
雇用枠の種類について
障がいのことを開示して就職する場合、障がいの特性上必要と企業に認められると、就業時間の短縮や就業時間内の通院などの配慮を求められます。障がい者雇用枠を利用すると面談の機会があり、働きやすい環境をより整えやすいメリットもあります。
ただし、障がい者雇用枠を利用するには障害者手帳が必要です。配慮可能な職種には限りがあるため、希望職種を選べるとは限りません。また、一般雇用枠で障がいを開示して就職した場合、配慮の範囲や考え方が企業によって異なるため、望む配慮を得られない可能性があります。
障がいのことを開示せず就職する場合、職種を選ばず就職できますが、基本的に上記のような配慮は受けられません。
障がいの有無へ開示する義務はないため、伝えるか伝えないかは本人次第です。人によって合う方法が異なるため、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
自分のできること・苦手なことを明確にする
自分にある障がいをよく理解し、できることとそうでないことを明確にすることが大切です。
学習障害の方は、自分の症状をはっきり認識しているケースが多く見られます。そのため、自分がどんなときにストレスを強く感じるのか、どんな作業に困るケースがあるかなど、自身としっかり向き合うことで就職時のミスマッチを防ぎやすくなります。
自分にある障がいを理解しておき、職場へ具体的に伝えておくようにすれば、ストレスを感じにくい職場へ就職できる可能性が高まるでしょう。
【学習障害の方が就職時に職場に伝えておきたいこと】
- どのような症状があるのか
- 負担の少ないのはどのような作業か
- どのような配慮をしてもらいたいか など
困った時に相談できる窓口が設置されている
困ったときに相談窓口があるかどうかは、学習障害の方が仕事を探す上で大きな要因です。相談できる窓口があれば、働く上での安心感につながります。
最近は、会社全体でメンタルヘルス対策に取り組み、相談窓口を設ける企業もかなり増えてきました。労働者が50名以上いる職場(事業場)では産業医の選任が義務づけられているため、健康上不安なことがあれば相談することも可能です。
また、障がい者向けの転職エージェントや就労サービス支援など、就職後も各種相談や面談などのアフターフォローが利用できるものもあります。就職後に不安な面が出てきたときには、ぜひ積極的に利用してみましょう。
学習障害の方が利用できる就労サービス

学習障害の方が仕事探しするにあたって、抱えている悩みや不安を相談できるさまざまなサービスがあります。具体的には、次のサービスが挙げられます。
【学習障害の方が活用できる就労サービス】
- 就職移行支援事業所
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- ハローワーク
- 転職エージェント
就労移行支援事業所
「就労移行支援事業所」は、病気や障がいが原因で求職中・離職中の方に対して、就労に必要な知識と能力を訓練して一般就労を目指す通所型の支援サービスです。就労移行支援事業所の利用は、障害者手帳の所持が必須ではなく「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。
地方自治体から指定を受けた施設で運営されており、令和2年現在で全国に3,301カ所となっています。
【就労移行支援事業所で受けられる支援内容】
- 一般就労への移行へ向けた訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着支援など
- 個別支援計画の進捗状況に応じた職場実習など、さまざまなサービスを組み合わせた支援
- 利用者ごとに24ヶ月以内で利用可能(必要性が認められた場合最大12ヶ月の更新可)
就労移行支援事業所では、職業スキル・体調管理・症状との向き合い方など、一人ひとりに合わせたサポートを受けられるのが特徴です。サービス終了後に一般就労へ移行した方の割合は54.7%(令和元年3)と、一般就労を目指す方にとっては利用価値の高いサービスです。
地域障害者職業センター
「地域障害者職業センター」は「独立法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が手掛ける事業です。専門的な職業リハビリテーションサービスを、障がい者の方に向けて提供しています。
各都道府県にそれぞれ1~2つずつ設置されており、受けられる支援内容は次の通りです。
【地域障害者職業センターで受けられる支援内容】
- 職業相談・職業適性の評価・職業リハビリテーション計画の策定
- 個別の課題に応じた職業準備支援
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)による個人の特性を踏まえた雇用支援
- 休職している方が職場復帰できるための課題の整理とリワーク支援 など
地域障害者職業センターでは、障がい者の方の特性に合わせた専門的な支援を幅広く受けられます。就職先の紹介や職業訓練は実施されておらず、就職や職場復帰を目指す方への職業相談がメインのサポートです。
発達障害の方向けに「発達障害者就労支援カリキュラム」が組まれており、「求職活動支援」「就労支援ネットワークの構築」を体系的に実施しています。
障害者手帳を持たない方でも利用できますが、雇用支援施策の適用される範囲が細かい部分で異なるケースがあります。詳細については、お住まいの地域の地域障害者職業センターへお問い合わせください。
障害者就業・生活支援センター
「障害者就業・生活支援センター」(なかぽつ・就ぽつとも呼ばれる)は、身近な地域において就業・生活における一体的な支援をおこなう機関です。18歳以上で、かつ「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「身体障害者手帳」のいずれかをもつ方であれば利用できます。
厚生労働省から委託された事業所が運営しており、令和4年4月1日現在、全国338カ所に設置されています。
受けられるおもな支援については、次の通りです。
【障害者就業・生活支援センターで受けられる支援内容】
- 就業面での相談支援(就業準備訓練、職場実習、職場定着に向けた支援など)
- 障がい者個人の特性を踏まえた雇用について、企業に対する助言
- 日常生活・地域生活に関する助言(日常生活の自己管理、地域生活、生活設計への助言など)
- 関係機関との連絡調整
障害者就業・生活支援センターは近隣の障がい者の方が対象の施設のため、より地域に密着したサービスとなっています。就職相談だけではなく生活相談も受け付けているため、生活の自立・安定を目指す方にマッチする支援といえるでしょう。
ハローワーク
「ハローワーク」は、厚生労働省が全国に設置している公共職業安定所で、令和4年4月現在、全国に544カ所あります。一般の求人窓口以外に、障がいについて専門的な知識を持つ担当者のいる専門窓口が設けられており、障害者手帳を持たない方でも窓口の利用は可能です。
おもなサービスは、次の通りです。
【ハローワークで受けられる支援内容】
- 職業相談・職業紹介
- 障がい者の方向け求人の確保
- 関係機関と連携した就職支援
- 採用面接時の同行・採用後の継続的な支援
ハローワークでは、おもに就業に関する支援が受けられます。就労支援機関と連携しているため、相談内容に応じて適切な機関の紹介を受けられます。就業の相談であれば、まずハローワークを訪ねてみて、適切な進め方を聞いてみるとよいでしょう。
転職エージェント
「転職エージェント」とは、専門のキャリアアドバイザーが求職者と企業を取り持って、転職を支援してくれるサービスのことです。転職エージェントには、障がい者の方の就職を専門で取り扱う「障がい者転職特化型」のところがあります。
【転職エージェントで受けられる支援内容】
- キャリアアドバイザーによるカウンセリングと転職活動全般のサポート
- 就職市場・業界情報の情報提供
- 書類添削・模擬面接などの採用試験対策
- 企業への応募や面接日程の調整
- 転職後のアフターフォロー
転職エージェントに登録することによって、就職前から就職後まで手厚いサポートが受けられます。ご自身の特性や症状などで求職活動に不安のある方でも、キャリアアドバイザーに相談しながら活動を進められるのが最大のメリットです。
障害者手帳が必要かどうかは、利用する転職エージェントによって異なります。登録する際に、必要かどうか問い合わせて確認しておきましょう。
まとめ
学習障害は比較的症状を自分で理解しやすいことから、有効な対策を考えやすい面もあります。その上で、自身の特性を理解し、働きやすい職場選びをすることが大切です。
自分にあった職場を探すにあたっては、さまざまな就労サービスが利用できます。支援内容はそれぞれ異なりますので、自分の求める内容が取り扱われているサービスを選ぶとよいでしょう。この記事を参考にして、自分に合った職場を見つけられるように応援しています。
| 【本記事監修者】 佐々木規夫様 産業医科大学医学部医学科卒業。 |