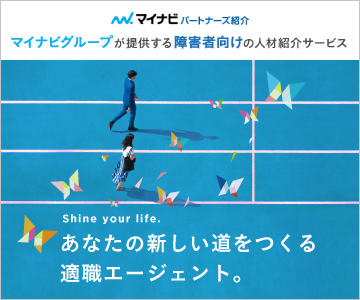2024年05月27日
発達障害の方が就職時に活用できる支援・サービス|考慮したいポイントも紹介!

目次
発達障害の方の中には、「就職できないのでは」「働いても長続きしない」という悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
これまでの職場や学校などで困った経験から、就職に不安になることもあると思います。しかし、自分の得意不得意を明確にすることや、支援機関を活用していくことで自分に合った働き方の選び方も見えてきます。
この記事では、得意不得意のまとめ方、活用できる支援機関、障がい者雇用枠で働くことなど、安定して働くための情報を紹介します。
発達障害とは
 発達障害とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。同じ障害名でも個性や発達の状況、年齢、環境などのさまざまな要因によって多彩な症状を呈します。
発達障害とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。同じ障害名でも個性や発達の状況、年齢、環境などのさまざまな要因によって多彩な症状を呈します。
発達障害の原因は現時点では解明されていませんが、先天的な脳機能の障がいという説が有力となっています。
発達障害の定義は複数ありますが、日本では2005年に施行された発達障害支援法第2条において以下のように定義されています。
| 【発達障害の定義】 「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」 (発達障害支援法第2条) |
発達障害の種類
発達障害はいくつかの種類に分かれています。また、同じ診断名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの障害を併せ持ったりすることもあります。
診断名だけですべてが決まるわけではありませんが、特性や傾向を知っておくことで対策をたてることにもつながりますので、参考にしていただければと思います。
【発達障害の種類】
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)/限局性学習症(SLD)
他にもチック症(トゥレット症候群)や吃音(きつおん)症も発達障害に含まれることがあります。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)とは、対人関係の困難やさ興味関心の偏りといった特徴がある発達障害のことです。
以前は自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群といった呼ばれ方をしていましたが、現在では自閉スペクトラム症という診断名が使われることが多いです。
対人関係の困難としては、例えば「相手の立場になったり、状況によって対応を変えることが苦手」「たとえ話などを理解できず、言葉を文字通り受け取る」といったことが特性から生じる場合があります。
興味関心の偏りは特定のことや行動にこだわりが強く出るために、「いつもと違う手順になるとストレスを感じる」「臨機応変な対応が苦手」などといったことがあります。
また、自閉スペクトラム症の方の中には、視覚過敏や聴覚過敏など感覚の過敏さ(または鈍麻)がある方もいます。
注意欠如・多動症(ADHD)
注意欠如・多動症(ADHD)とは、「一つのことに注意向けることが困難」という「不注意」と、「落ち着きがない」「思いついたことをすぐ行動する」といった「多動・衝動性」の特性が見られる発達障害です。
不注意特性としては「一つのことに注意を向けることが困難」であることから「忘れ物が多い」「よくケアレスミスをする」といった傾向があります。
多動・衝動性の特性では「じっと座っていることが難しい」「思いついたことをすぐ言葉にしたり、行動に移すことが多い」といった傾向があります。
これらの特性は人によって現れ方が異なっており、不注意が出やすい方もいれば多動・衝動性が出やすい方もいて、また混在している場合もあります。
学習障害(LD)/限局性学習症(SLD)
学習障害(LD)は、限局性学習症(SLD)とも呼ばれていて、ある特定の学習にだけ苦手がある発達障害のことです。
学習障害には「読字障害」「書字障害」「算数障害」といった種類があります。
読字障害は文字を読むことに対する困難で、「文字を一つ一つ区切って読む」「行間が狭いと読みづらくなる」「文章を読んでいると疲れやすい」といった傾向があります。
書字障害は文字を書くことに対する困難で、「画数の多い漢字を書き間違える」「「は」と「わ」など同じ読み方の文字を書き間違える」「めとぬなど形が似ている文字を書き間違える」といった傾向があります。
算数障害は数字に関する困難で、「簡単な計算を暗算することが難しい」「足し算と掛け算が混ざった計算が苦手」といった傾向があります。
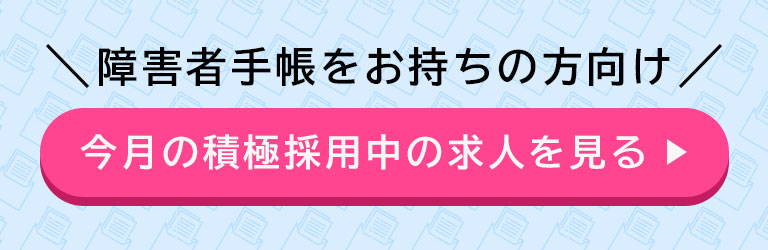
発達障害によるお困りごとや悩み

発達障害の方が働く上でよくある困りごとを紹介します。
【発達障害による困りごとや悩みの例】
- あいまいな指示が苦手など業務指示で困ることがある
- 業務の進め方(優先順位をつけるのが難しい、マルチタスクが難しいなど)に苦手がある
- 感覚の過敏さによって、疲労を感じやすい傾向がある
- 複数人の会話だと理解がしづらいなど対人・コミュニケーション面で難しさを感じることがある
例えば、「なるべく早くお願い」などあいまいな指示だと混乱してしまうことや、電話が常に鳴っている環境だと聴覚過敏によってひどく疲れてしまう、といった困りごとがあります。
こういった困りごとが続くことで精神的にも負担となり、うつ病など二次障害を併発することにもつながることがあります。
上記は、あくまで一例であり、発達障害の特性は診断名に関わらず人によってさまざまです。また、個人の性格や環境によって困りごとも変わってきます。
傾向として参考にしながら、自分自身がどのようなことに困るのか、ストレスを感じるのかといったことを把握して対策を立てていくことが仕事をするうえでも大事です。
発達障害の方が就職する時に考慮したいポイント
 発達障害の特性によって前の章で紹介したような悩みがあり、就職に不安を覚える方もいると思います。
発達障害の特性によって前の章で紹介したような悩みがあり、就職に不安を覚える方もいると思います。
そういった場合は以下のような点を考慮することで、働きやすい職場を見つけることができるかもしれません。
【発達障害の方が考慮したいポイント】
- 一般枠か障がい者雇用枠か
- 自分の得意・不得意を明確にする
一般枠か障がい者枠か
まずは、働く環境を選んでいくために、発達障害の方が働く場合に選択肢としてある雇用枠を紹介します。
【雇用枠の選択肢】
- 一般雇用枠(障がいオープン):障がいがあることを開示して就職する
- 一般雇用枠(障がいクローズ):障がいがあることを開示せずに就職する
- 障がい者雇用枠:障害者手帳を保有している人が対象の雇用枠
発達障害のある方をはじめ、障がいのある方が職場に障がいについて伝えて働くことを「障がいを開示する」または「障がいオープン」といった言い方をすることがあります。
一般雇用枠(障がいオープン)
一般雇用(障がいオープン)から説明します。障害あるなし関わらず誰でも応募できる求人で働く一般雇用枠で、職場の方に障がいのことを伝えて働く場合が該当します。
職場に開示して働くことで、職場に「合理的配慮」を求めることができます。合理的配慮とは、障害者雇用促進法によって保障された権利で、障がいの特性上難しい業務などに企業が一定の配慮を行うことです。尚、一般雇用枠においては配慮の範囲や考え方が企業によっても異なるため、一般枠では必ずしも望む配慮が十分に得られるとは限りません。
一般雇用枠(障がいクローズ)
一般雇用枠で障害について伝えないことを「障がいクローズ」と呼ばれています。
障がいのことを開示しないために、「通院日に休みを取得する」といった配慮を得ることは難しい傾向があります。
その代わりに一般雇用枠の求人の数自体は多く、職種や業務内容、勤務地などの選択肢が多くなっています。
障がい者雇用枠
障がい者雇用枠とは「障害者手帳」を所持している方が応募できる雇用枠のことです。
働く側としては合理的配慮を求めることができるほか、雇う側も障がいのある方が応募してくることを想定しているため、障がいのある方に働きやすい環境となっている傾向もあります。
例えば、「聴覚過敏がある方がイヤホンをしながら仕事をする」「通院日に休みを取得しやすくする」といった配慮の例があります。
障がい者雇用の担当者がいて、入社後も体調や業務についての確認がある、面談の機会が多い、就労支援機関との連携がとりやすいなどの障がいのある方が働く上でのサポートが受けやすいことがあります。
障害者手帳には種類があり、発達障害の方は「精神障害者保健福祉手帳」が対象となります。取得には申請が必要になりますので、詳しくはお住まいの自治体の障害福祉窓口へお問い合わせください。
自分に合った環境を見つけることが大事
どういった働き方が合っているかは、その人によって異なります。「配慮があった方が安心」という方もいれば、「障がいのことを気にしないで働く方が楽」という方もいると思います。
さまざまな働き方があることを知ったうえで、自分にとって働きやすい環境を探していくことが大事です。
自分の得意・不得意を明確にする
発達障害の方は、特性によって仕事で得意不得意が大きく分かれることがあります。
得意分野を生かせる仕事であれば働きやすくなりますし、逆に不得意な分野が多い職場であればストレスを強く感じることにもなりかねません。
例えば口頭での業務指示に難しさを感じる方は、主にメールやチャットなど文字でのやり取りをする職場であれば不得意を感じることが少なくなります。
自分自身の得意不得意が明確になれば、就職活動する際に応募する求人を選ぶ助けにもなりますし、働いた後に難しい業務があったときも職場の方と具体的な相談がしやすくなります。
明確にする項目
得意不得意を明確にするといっても、何から手を付けていいのか迷ってしまう方もいると思います。
ここでは障害者職業総合センターが紹介している、障がいの特性をまとめるための「ナビゲーションブック」から指標をお伝えします。
ナビゲーションブックの一例では
- 作業面:正確さ、スピードなど
- 対人面:複数人での会話、あいまいな言葉が苦手など
- 思考・行動面: マイナス思考が多い、衝動性があるなど
- 体調面:疲労を感じる環境(満員電車、騒音など)、リラックスできる環境(個室、好きな音楽を聴くなど)など
という項目ごとに得意と不得意を記載しています。
迷った場合はこの項目を参考に、自身の中でこれまでの経験から得意不得意を書きだしていくといいでしょう。
サポートを受ける
一人で得意不得意を考えるのが難しいと感じる場合は、就労支援機関などのサポートを受ける方法もあります。
自分では苦手と思っていても、他者から見たら十分にできているということも少なくありません。そういった客観的な視点を入れることで、自分の得意不得意が整理しやくなっていきます。
先ほど紹介したナビゲーションブックも自身だけでなく、支援者と進めていくことを推奨しています。就労支援機関や障がいのある方向けの人材紹介サービスの活動も視野に入れておくといいでしょう。
発達障害の方が活用できる就労支援

発達障害のある方が働くことで困ったときに活用できる就労サービスがあります。
【発達障害の方が活用できる就労サービス】
- 就労移行支援事業所
- 発達障害者支援センター
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- ハローワーク
- 障がい者向け人材紹介サービス
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障がいのある方が企業などに就職するために、24か月(標準期間)の中で必要なスキルを取得し就職を目指していく場所です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、社会福祉法人やNPO法人の他、民間企業が運営しているケースもあり、令和2年10月1日時点で全国に3301事業所設置されています。
就職先を紹介する機関ではないため、求人探しは利用者自身で行い、スタッフはそのサポートをするという位置づけで支援を行っています。
就労移行支援事業所で受けられる支援内容
- 応募書類作成・面接練習:応募書類の添削や、面接のアドバイス・模擬面接などを行い、実際の面接に同行する場合もあります。
- 職場実習:実際の職場で働く体験を行い、自身に合った業務内容・指示理解・職場環境などを整理していきます。
- コミュニケーション訓練:職場でのビジネスマナーや円滑なコミュニケーション方法などを、座学やロールプレイを通じて身につけていきます。
- 業務訓練:パソコン訓練や、作業訓練など業務面のスキル向上を目指す訓練を提供しています。
- 障がい理解:自身の障がい特性の理解や、得意不得意の整理、合理的配慮の求め方などの支援をします。
民間の事業所も多くあり、「資格取得をサポート」「在宅支援が中心」「発達障害の方に特化」など事業所によって特色が異なっている点が特徴としてあります。
見学や体験ができる場合がほとんどですので、まずは自分にマッチするか試してみるといいでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターとは、発達障害者支援法をもとに設置されている支援機関です。
年齢を問わず発達障害者の方に医療、福祉、労働といった関係機関と連携しながら、地域における総合的な支援を提供しています。
都道府県・指定都市または、社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営を行っており、令和4年8月時点で全国87ヶ所あります。
発達障害者支援センターで受けられる支援内容
- 相談支援:コミュニケーションの悩みなど日常生活でのさまざまな相談を受け付け必要なアドバイスなどを行います。
- 発達支援:発達障害に関する相談に対して、アドバイスや発達検査の実施などを行います。
- 就労支援:就職を希望する方の相談を受け付け、他の就労支援機関との連携や職場との調整を行います。
発達障害者支援センターの特徴は、発達障害の方に向けて日常生活と社会生活の総合的な支援が受けられる点です。また、ハローワークなど他の支援機関との連携も行いながら支援を進めていきます。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害者雇用促進法に基づき各都道府県に設置されている支援機関です。
ハローワークといった他の支援機関や企業などと連携して、「職業リハビリテーション」を提供しています。
職業リハビリテーションとは、障がいのある方が適した職場に雇用され、働き続けることや能力を向上させることを通して社会参加することを目的とした取り組みのことです。
地域障害者職業センターでは、職業リハビリテーションとして、「職業評価」「職業準備支援」「職場適応援助者支援事業」といった支援を行っています。
地域障害者職業センターで受けられる支援内容
- 職業評価:これまでの業務経験、障がいの特性、希望する就労条件などをヒアリングして、「職業評価」を行って支援計画を立てていきます。
- 職業準備支援:職業評価によって作成した計画に基づいて、センター内で業務スキルの訓練、働くための講座開催、職場でのコミュニケーション練習といったさまざまな支援を行います。
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業:ジョブコーチといって障がいのある方が働きやすくなるように、職場と連携しながら実際の業務の進め方や職場環境への働きかけをするスタッフを職場に派遣する支援を行います。
地域障害者職業センターでは、職業リハビリテーションの観点から、障がいのある方の就職や働き続けることの専門的な支援を受けることができる点が特徴です。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターとは、障害者雇用促進法に基づき設定されていて、障がいのある方の就業面だけでなく、日常生活の相談も受けつけている支援機関です。
令和4年4月1日時点で全国338か所設置されており、地域によって「なかぽつ」や「しゅうぽつ」といった呼ばれ方をされることがあります。
障害者就業・生活支援センターで受けられる支援内容
- 就職活動の支援:就職活動の支援として、働く悩みの相談から、特性による困りごとや得意不得意の明確化、書類の添削や面接の練習といったサポートを行っています。
- 定着支援:就職した後も働き続けるために、同僚との人間関係や業務についての悩み相談や、センターのスタッフにより職場環境に働きかけといったサポートをしています。
- 生活面の支援:生活リズムや食事などの生活習慣・健康管理へのアドバイスや、金銭管理、住居、年金などの日常生活を送る上での困りごとに対してサポートを行っています。
障害者就業・生活支援センターでは仕事のみならず生活にもサポートを行っている点が特徴です。
ハローワーク
ハローワークは正式名称「公共職業安定所」といい、厚生労働省設置法に基づき各都道府県に設置されている行政機関です。
令和4年4月1日で全国に544ヶ所あり、求人情報の提供や雇用保険の手続き等、雇用に関するさまざまなことを取り扱っています。
ハローワークには障がいのある方に向けの窓口が設けられていて、専門スタッフへの相談や、障がい者雇用枠への応募、職業指導等を受けることができます。
ハローワークで受けられる支援内容
- 障がいの専門スタッフによる支援:障がいのある方向けの窓口では、専門知識を持ったスタッフが担当としてつき、就職のから働いた後まで支援を行っています。また、一部では発達障害者雇用トータルサポーターという、発達障害の方の就職の専門スタッフがいる場合があります。
- ハロートレーニング:ハロートレーニングは「公共職業訓練」とも呼ばれる、職業スキルや知識の取得を目的とした公的な訓練のことです。障がいのある方向けのコースがあり、手続きはハローワークで行います。
- 障害者トライアル雇用制度:3か月~6か月といった一定の期間実際に働いてみることで、働く側と雇用側がそれぞれの理解を深めたうえで入社を決める制度です。
ハローワークでは就職のサポートだけでなく、失業保険の手続きなど雇用に関する全般的な業務を行っている点が特徴です。
転職エージェント
転職エージェントとは、キャリアアドバイザーなどの専門家が相談者の希望をうかがったうえで、マッチする求人を紹介していくサービスです。
求人検索サイトと異なり、担当者が面談や手続き代行を行うなどきめ細かいサービスが特徴です。転職エージェントの中には障がいのある方向けのサービスを提供している企業もあります。
【転職エージェントサービスで受けられる支援内容】
- キャリア相談:キャリアアドバイザーが相談者からこれまでの経験や、障がい特性、希望する条件などを聞き、整理していきます。
- 求人の紹介:キャリア相談をしたうえで、その人に合った求人の紹介を受けることができます。
- 応募書類添削・面接のアドバイス:応募する書類の添削支援や、面接時のアドバイスなどを行います。
- 面接や入社の日程調整の代行:面接の日時や、内定後の日程調整などの手続きの代行を行います。
- 入社後の職場定着フォロー:入社後も定期的に状況確認を行い、困りごとがあれば入社企業との調整を行います。
障がいのある方向けの転職エージェントでは、上記の他にカウンセリングを通して得意不得意や配慮の整理を行うなどの特徴があります。
また、実際に発達障害の方が働いている事例を聞くこともできる場合があり、自身の働き方のイメージもつかめるというメリットもあります。
まとめ
この記事では働きやすくしていくポイントについて紹介しました。発達障害と一口にいっても、特性は人によって異なっています。
これまで職場や学校などで環境と合わずに困難があった方は、自身の得意不得意を明確にすることや、働き方の選択肢を広げていくことが、働きやすい職場を見つけるために大事です。
一人で全部を行うのが難しいと感じた方は、発達障害の方が活用できる支援機関や転職エージェントの利用を検討してみるといいでしょう。
| 【本記事監修者】 佐々木規夫様 産業医科大学医学部医学科卒業。 |